鹿児島大学農学部との共同研究。
卒論発表会には参加できなかったが、別途で時間をわざわざ設けてもらった。
「粉砕玄米を給与した森林豚(ふぉれすとん)の産肉性」
「林内放牧の行動ならびに産肉特性の解明」
2人の学生が飼料米を使って研究をしてくれました。
飼料米は食べるようになってくれさえすれば、配合飼料には劣らず発育することも分かった。
70%飼料米も十分可能。
また、お米を食べさせることでオレイン酸が上がり、軟脂などが発生すると言われるリノール酸が減少するという結果も得られた。他の文献でも出ているようだが、自分たちでそれが立証できたことは大きい意味がある。
国産できる穀物を十分に使いこなせる事が重要だ。
現在は国内の食は米を食べずパンが多い。
工場の製造量は増える一方のようだ。
リキッド飼料を製造している外食産業もパンの製造を始めたらしい。
おかげ様で農場でも現在はリキッド飼料と配合飼料と甘藷をベースに、一部パンや麺くずを飼料として与えている。
面倒は掛かるが、コストダウンにつながることは有難い。
しかし一方で、輸入小麦が今後どう変化していくか分からない中、パンや麺に依存する生産が確立できるのは今だけかもしれない。10年後はどうなっているのか。
現在の日本の食生活そのものが、諸外国との事情によって変化せざるを得ないだろう。
当然、副産物も変わる。
余っていたものが余らなくなる。
最も魚を食べる日本、鹿児島になってるかもしれない。副産物も魚中心に?
なんと言っても日本の穀物は「お米」、鹿児島の産物は「甘藷」。そして「発酵」という文化がある。
飼料として、タンパク源を地元からどう補ってやれるかも課題である。
このタンパク不足を来年の学生は大学内で発生する食品残さを発酵して飼料化し、補うことで発育や肉質に与える影響をつきつめていく研究をする予定だと聞いた。
発育だけではなく、肉質はそれ以上に厳しく追及していかなければならない。売るからには質の向上と安定は不可欠要素であることは、百貨店で店頭販売させてもらったことで十分に学べたはずた。
まだ、自分の農場では飼料米を十分に活用できる体制づくりが出来ていないが、今のうちに学生たちの研究成果をお借りして、根拠作りが出来ていけばいい。
来年度の研究に面白いテーマも浮上しそうだ。
遊休地では山羊とガチョウを使って除草効果を狙っているが、ここに豚が登場?
来年の学生の話を聞いてると、なんか面白そうである。
いつもありがとうございます。
先生方にもお世話になりホントにすみません。
豚の革が人間の子供の皮膚に一番相性が良い、なんて研究してくれるところはないものか。
豚の胎盤も今じゃ化粧水で当たり前になったくらいだ。
豚の皮膚や臓器は既に役に立ち始め、人間の生理学的にも応用できそうな研究も進められてますね。
豚の捨てるところは鳴き声だけ、なんて言われたくらいだから、
豚がもっと国内で、地域で役に立つ存在になってもらいたい。
豚が食と環境、観光、健康に関わり、ヒトにとって大切なパートナーへ。
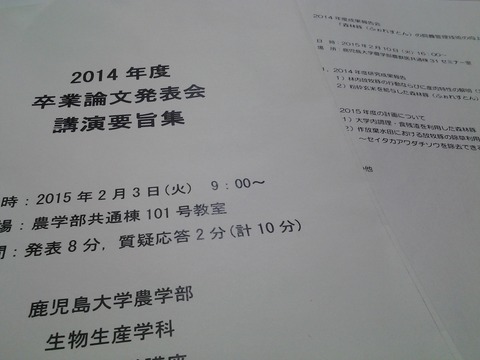

卒論発表会には参加できなかったが、別途で時間をわざわざ設けてもらった。
「粉砕玄米を給与した森林豚(ふぉれすとん)の産肉性」
「林内放牧の行動ならびに産肉特性の解明」
2人の学生が飼料米を使って研究をしてくれました。
飼料米は食べるようになってくれさえすれば、配合飼料には劣らず発育することも分かった。
70%飼料米も十分可能。
また、お米を食べさせることでオレイン酸が上がり、軟脂などが発生すると言われるリノール酸が減少するという結果も得られた。他の文献でも出ているようだが、自分たちでそれが立証できたことは大きい意味がある。
国産できる穀物を十分に使いこなせる事が重要だ。
現在は国内の食は米を食べずパンが多い。
工場の製造量は増える一方のようだ。
リキッド飼料を製造している外食産業もパンの製造を始めたらしい。
おかげ様で農場でも現在はリキッド飼料と配合飼料と甘藷をベースに、一部パンや麺くずを飼料として与えている。
面倒は掛かるが、コストダウンにつながることは有難い。
しかし一方で、輸入小麦が今後どう変化していくか分からない中、パンや麺に依存する生産が確立できるのは今だけかもしれない。10年後はどうなっているのか。
現在の日本の食生活そのものが、諸外国との事情によって変化せざるを得ないだろう。
当然、副産物も変わる。
余っていたものが余らなくなる。
最も魚を食べる日本、鹿児島になってるかもしれない。副産物も魚中心に?
なんと言っても日本の穀物は「お米」、鹿児島の産物は「甘藷」。そして「発酵」という文化がある。
飼料として、タンパク源を地元からどう補ってやれるかも課題である。
このタンパク不足を来年の学生は大学内で発生する食品残さを発酵して飼料化し、補うことで発育や肉質に与える影響をつきつめていく研究をする予定だと聞いた。
発育だけではなく、肉質はそれ以上に厳しく追及していかなければならない。売るからには質の向上と安定は不可欠要素であることは、百貨店で店頭販売させてもらったことで十分に学べたはずた。
まだ、自分の農場では飼料米を十分に活用できる体制づくりが出来ていないが、今のうちに学生たちの研究成果をお借りして、根拠作りが出来ていけばいい。
来年度の研究に面白いテーマも浮上しそうだ。
遊休地では山羊とガチョウを使って除草効果を狙っているが、ここに豚が登場?
来年の学生の話を聞いてると、なんか面白そうである。
いつもありがとうございます。
先生方にもお世話になりホントにすみません。
豚の革が人間の子供の皮膚に一番相性が良い、なんて研究してくれるところはないものか。
豚の胎盤も今じゃ化粧水で当たり前になったくらいだ。
豚の皮膚や臓器は既に役に立ち始め、人間の生理学的にも応用できそうな研究も進められてますね。
豚の捨てるところは鳴き声だけ、なんて言われたくらいだから、
豚がもっと国内で、地域で役に立つ存在になってもらいたい。
豚が食と環境、観光、健康に関わり、ヒトにとって大切なパートナーへ。
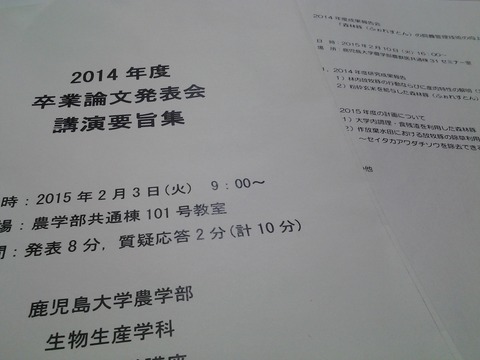




顔が見えないのでネットでブランド品を購入するのは不安。
でもこのように真心を込めてきれいに包装されて届くととてもすがすがしい思いです。嬉しい買い物でした。
ロレックス ヴィンテージ 名古屋 https://www.kopi66.com/protype/list.aspx?page=2&id=166